はじめに:「円満退社」は、あなたの未来のための、大切な準備です
「今の職場、もう辞めたい…でも、なんて伝えたらいいんだろう…」
「師長に退職を切り出すなんて、想像するだけで気が重くなる…」
看護師として働いていると、誰しも一度はこんな風に悩むことがあるかもしれません。
こんにちは。
看護師歴20年、これまで2度の転職を経験してきたヒロユキです。
退職は、「ただ辞める」という作業ではありません。
それは、次の職場で、あなたがもっと自分らしく働くための第一歩です。
看護の現場では「辞めます」と伝えるだけで、空気が張り詰めたり、人間関係が変わったり…
本来なら前向きな決断が、なぜか“後ろめたさ”に変わってしまうことがあったりしますよね。
そこで、この記事では、
「どうすれば揉めずに、スッと辞められるか?」
「本音を飲み込みすぎずに、でも角が立たない伝え方はあるのか?」
そういった悩みに対して、現役の看護師としてのリアルな経験と、実践的な工夫を交えながら、お伝えしていきます。
- 師長と気まずくならない退職の伝え方のコツ
- 引き止めへの対処法
- 最後まで好印象で終わるための心遣いポイント
- スムーズに退職するための”最後の切り札”など
「退職」が、あなたが自分らしく働くためのきっかけになりますように。
 ヒロユキ
ヒロユキこの記事が、少しでもお役にたてば、嬉しく思います!
退職の流れをざっくり確認:まずは全体像をつかもう
退職を考え始めたとき、まず「何から手をつければいいの?」と悩みますよね。
そんなあなたのために、まずは退職までの流れを7つのステップでご紹介します。
- STEP 1:就業規則の確認
- STEP 2:退職の意思を、上司に伝える
- STEP 3:退職日を正式に決定する
- STEP 4:退職届を正式に提出する
- STEP 5:責任ある業務の引き継ぎ
- STEP 6:最終出勤日を迎える
- STEP 7:退職後の必要な手続き



それでは、今からこの7つのステップの一つひとつを、詳しく解説していきますね!
【第一章】準備編:交渉の前に、まず「ルール」と「計画」を固める
退職交渉をスムーズに進めるために、最初にやるべきは「準備」です。
勢いで「辞めます!」と伝えてしまう前に、冷静に段取りを組むことが、後悔のない退職への第一歩です。
まず「就業規則」を確認しよう
退職には、病院ごとのルールが存在します。これを無視して話を進めると、思わぬトラブルになることもあります。
特に、以下の2点は必ず確認しましょう。
- 退職の申し出時期:「退職希望日の〇ヶ月前までに申し出ること」というルールが明記されていないか確認しましょう。
- 有給休暇の取り扱い: 未消化分の買い取りがあるか、有給消化にどこまで応じてもらえるかなど、職場によって異なります。



この「有給消化」に関しては、別の記事で、さらに詳しく解説しています。あなたが損をしないためにも、ぜひご確認ください!


「法律」と「現実」のギャップを知っておく
法律上は、退職の申し出日から14日(休日・祝日も含む)が経過すれば、辞めることは可能です。
しかし現実の現場では──
「今の新人さんが独り立ちするまでいて欲しい」
「来年度の採用者の見込みがついてからにして欲しい」
「今やっているあなたの仕事をしっかり引き継げるようになってからにして欲しい」
といった、“病院側の事情”が押し寄せてきます。
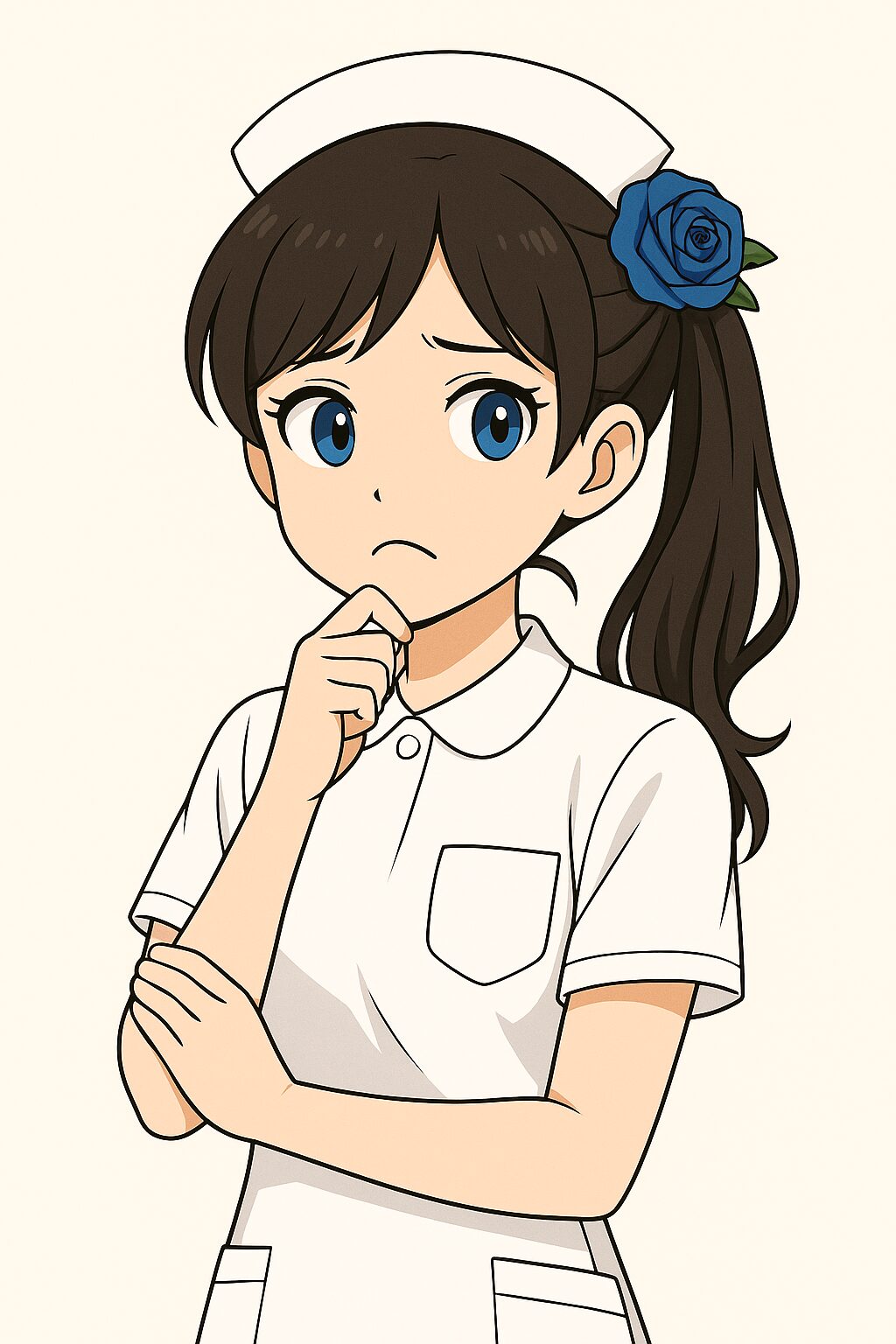
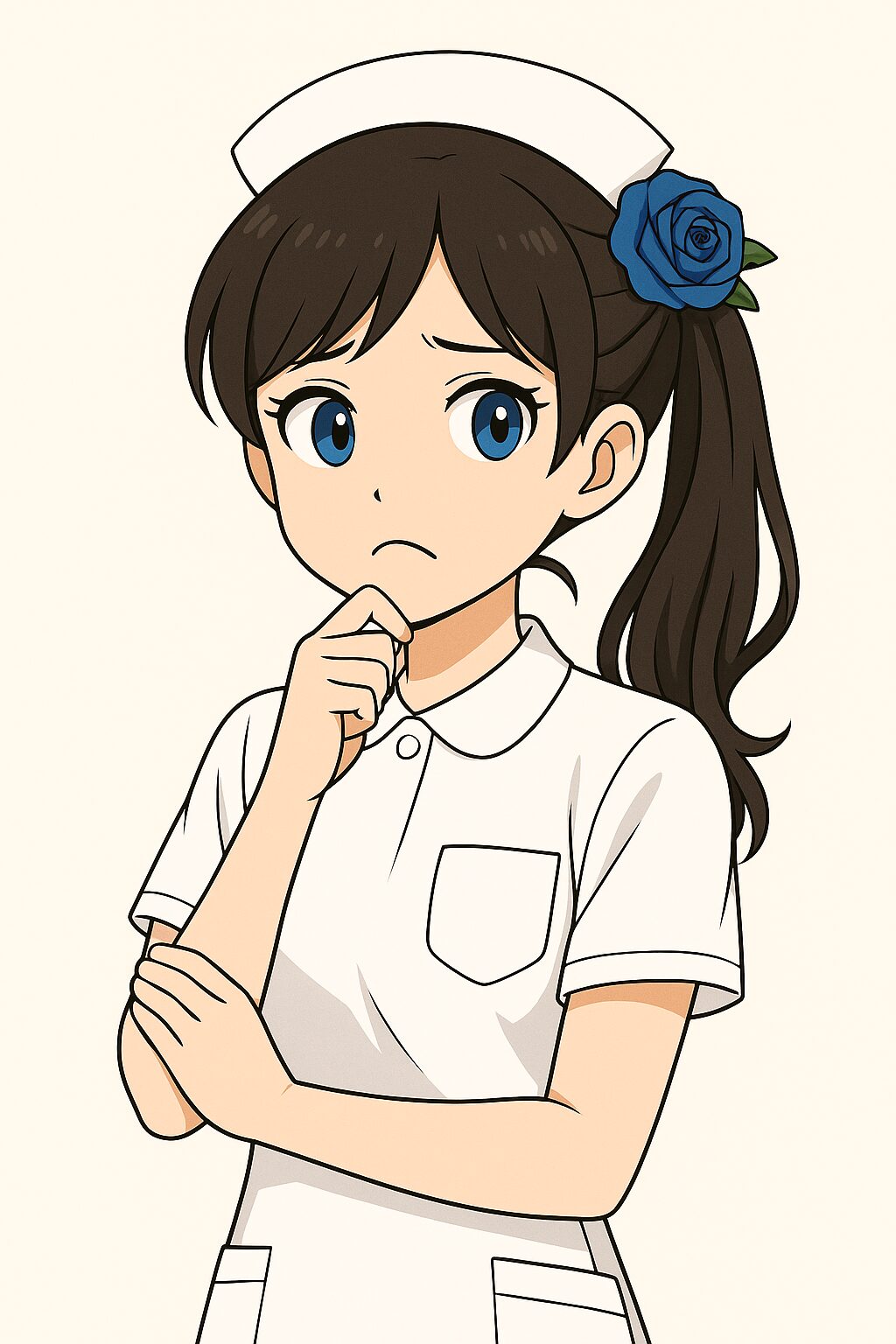
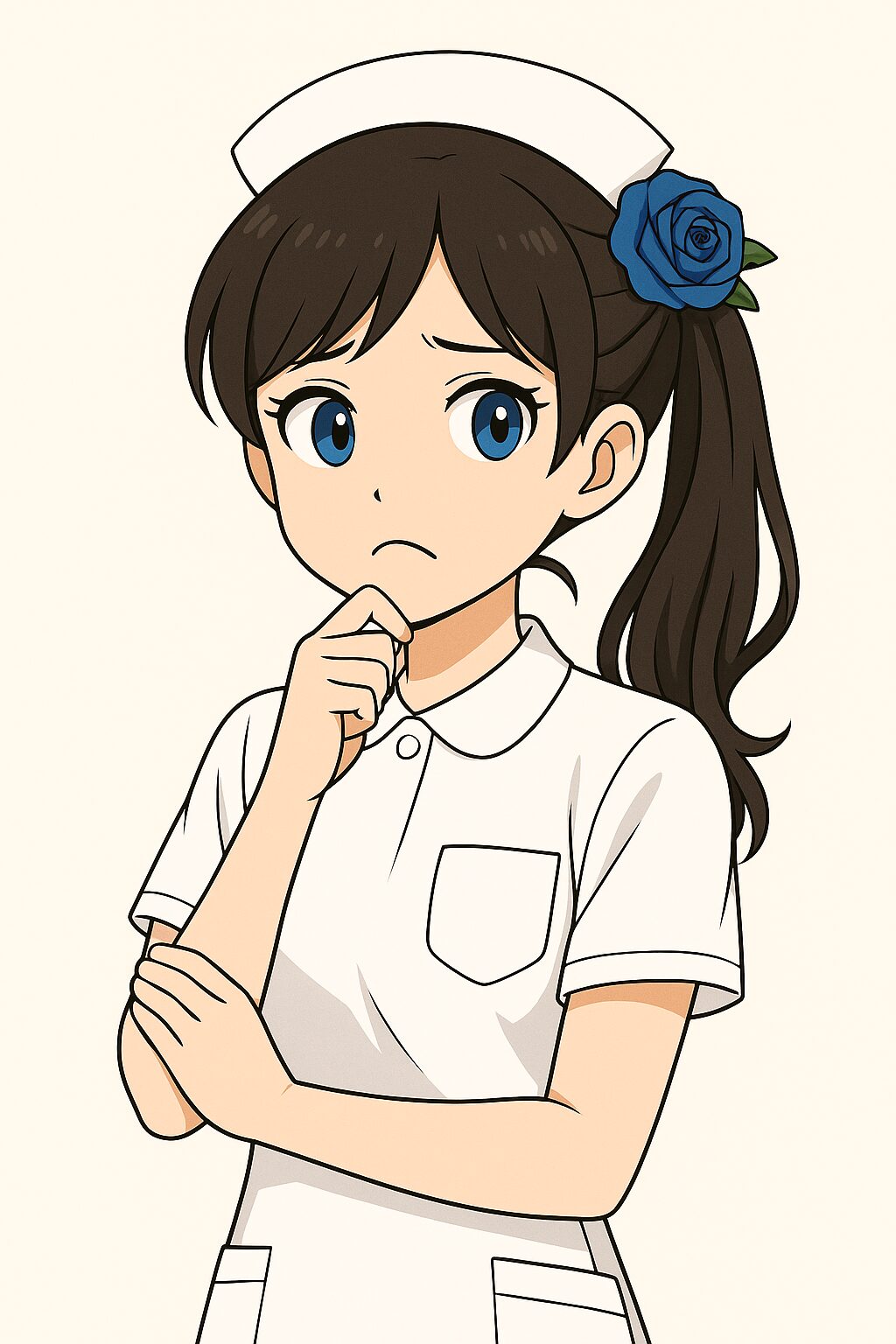
実際、多くの病院では「退職は3ヶ月前までに」というのが、暗黙のルールになっていますよね。
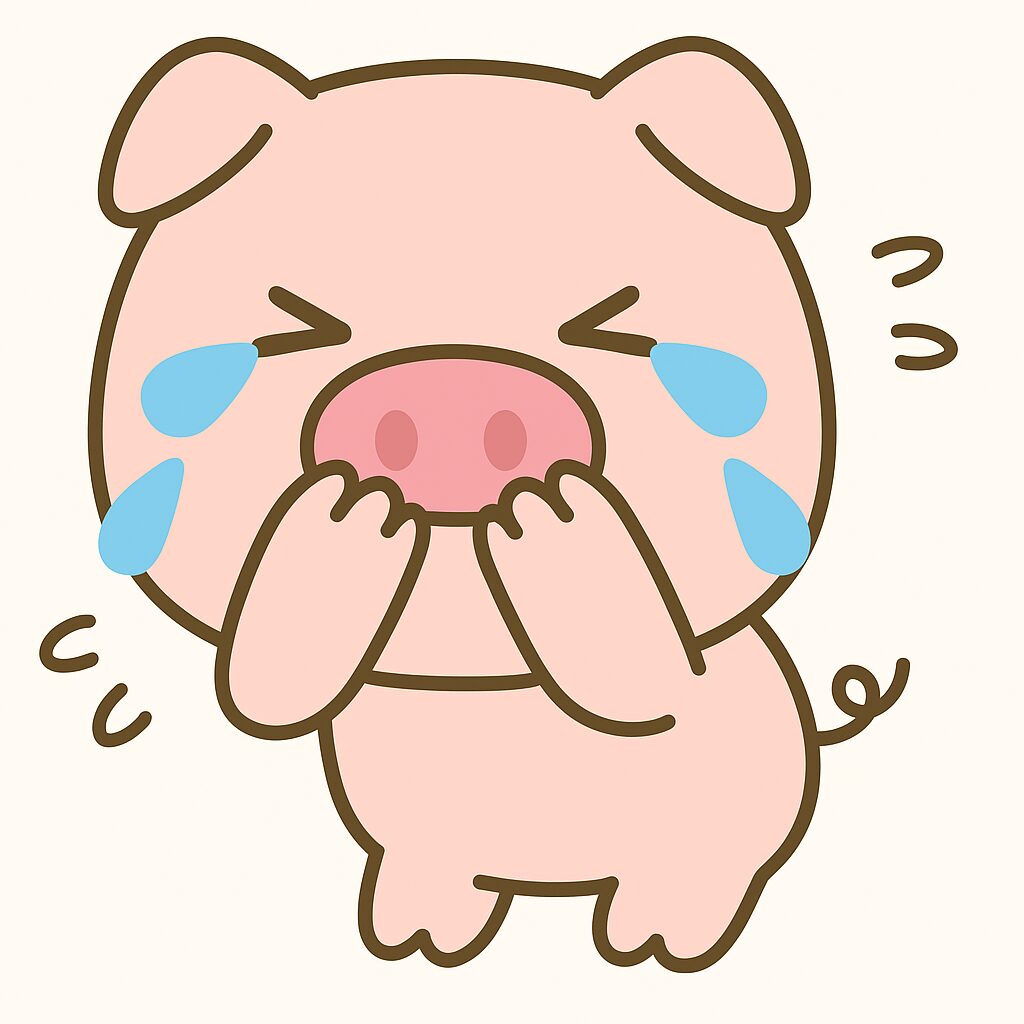
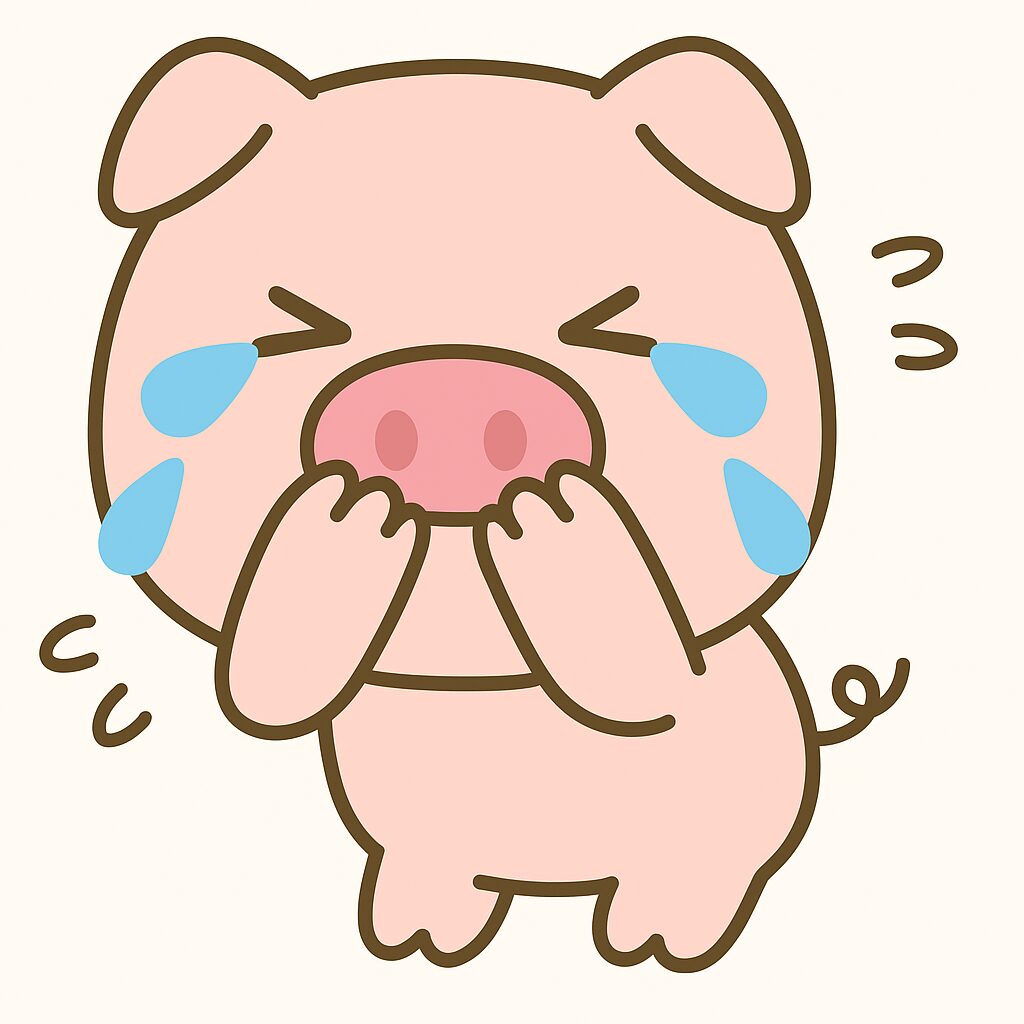
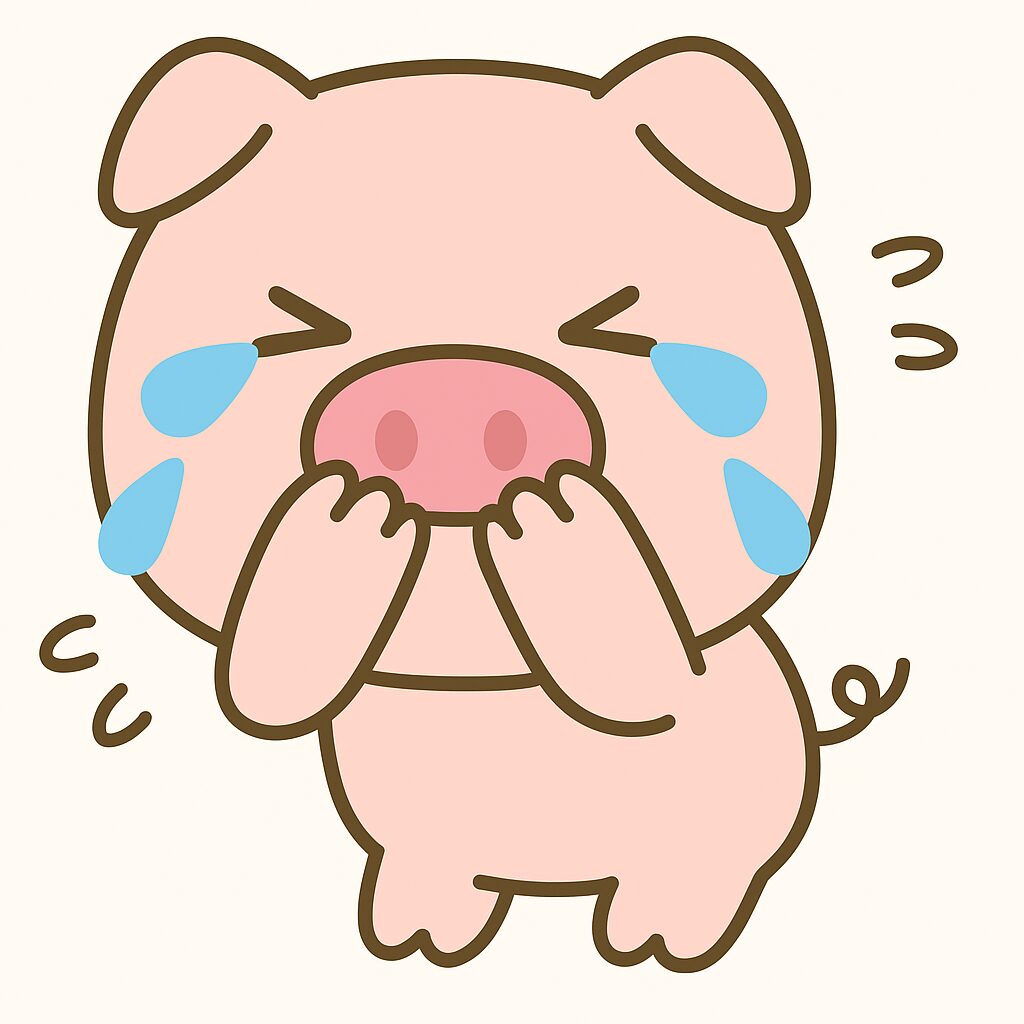
ひどい場合には、「退職は、1年前に申し出てください」なんていう、
ルールがあったりします。



これらのルールには法的な強制力はありません。
だからこそ大切なのは、「法律」と「就業規則」、両方を知ったうえで、
冷静に交渉する姿勢です。
「きちんと調べた上で伝えている」という態度が、相手の印象を大きく
変えます。
「退職スケジュール」は、ボーナスを基準に逆算する
いざ辞めようと思っても、タイミングを間違えると、ボーナスを受け取れない可能性があります。
退職タイミングの“かしこい決め方”は、以下の手順です。
- まず、ボーナス支給日を確認する:(例:夏は7月10日、冬は12月10日など)
- 支給が確定し、口座に入金されたのを確認した、”翌日以降”に、退職の意思を伝える
この順番を守ることで、金銭面での損失を防ぎつつ、円満な退職につなげることができます。
退職時のボーナス、本当にもらえる?
「辞めるといったら、ボーナスがもらえないって聞いたことあるけど本当?」と不安な方へ。
実は、ボーナスの支給には「就業規則の確認」や「ボーナス査定期間との関係」など、
意外と複雑なルールがあります。



退職時のボーナス支給についても、別記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
【第二章】交渉編:その「伝え方」が、あなたの未来を決める
準備が整っても、実際に「退職を伝える」というのは、誰にとっても緊張する瞬間です。
頭の中では決まっていても、「なんて切り出せばいいんだろう…」「怒られたらどうしよう」と、不安でいっぱいになりますよね。
でも、大丈夫。
ここでは、実際に私や周囲の看護師たちが経験してきた“リアルな工夫”をもとに、
- 上司に切り出すタイミングや伝え方
- 誰もが悩む「退職理由」のベストな伝え方
を、わかりやすくお伝えしていきます。
直属の上司への「伝え方」が、9割を決める
まずは、「誰に」「どんな場面で」「どう切り出すか」が大切です。
- アポイントの取り方:場所とタイミングに気をつけよう
決して、ナースステーションのど真ん中で「あの…辞めたいんですけど」なんて切り出してはいけません(笑)
周りのスタッフに余計なことで勘ぐられないように、
「師長、お忙しいところ申し訳ありません。今後の私のキャリアについて、少しご相談したいことがあります。業務終了後に、個室で5分ほど、お時間をいただくことは可能でしょうか?」と伝えましょう。 - 伝えるべき4つのポイント
- 感謝:「これまで、大変お世話になりました」
- 退職の意志:「退職させていただきたいと考えております」←相談ではなく「報告」としての明確な意思を伝える。
- 退職希望日: あらかじめ決めておいた具体的な退職希望日
- 責任感:「引き継ぎは、責任をもって行います」という、社会人としての姿勢。



この4点を、簡潔かつ丁寧に伝えるだけで、印象がガラリと変わります。
誰もが悩む「退職理由」の伝え方〜正直者は損をする?〜
「退職理由、正直に言っていいのかな?」
「本当は人間関係がしんどいけど…」
そんな風に悩んでいませんか?
多くの人がつまずくのが、“本音”と“伝えるべき理由”のバランスです。
不満をそのまま伝えるのは避けた方がいい
「人間関係が最悪すぎて…」
「もう限界です」
という言葉、あなたの正直な気持ちかもしれません。
ですが、そのまま伝えてしまうと、以下のような“逆効果”が生まれることがあります。
🔍 不満を伝えるリスク
① 感情的に受け取られやすい
「私の管理の仕方が悪いっていいたいの?」「愚痴にしか聞こえない」と、師長が防衛的になってしまう。
② 他のスタッフへの影響を警戒される
この理由が広まったら、他のスタッフも影響を受けるのでは…と懸念される。
③ 退職後に悪い印象が残る
看護の世界は狭く、再会や紹介、復職の可能性もあります。
そのときに、「あのとき辞め方が悪かった人」
というラベルが残る可能性もゼロではありません。
ではどう伝えるのがベスト?
ポイントは、不満ではなく「前向きな理由」や「自分の都合」にフォーカスすることです。
「誰かを責めるのではなく、自分のために選んだ道」──
このスタンスが、一番伝わりやすく、角が立ちません。
【そのまま使える、退職理由の例文】
① ポジティブ型:「スキルアップ」や「新しい挑戦」を理由にする
【例文:看護観の違いを伝える場合】
「お時間をいただきありがとうございます。これまで、こちらの急性期病棟で多くのことを学ばせていただき、本当に感謝しています。その中で、より患者さんと、じっくり向き合える看護をしたいという思いが強くなり、以前から興味のあった、◯◯の分野に挑戦したいと考えるようになりました。大変勝手なのですが、〇月〇日をもって、退職させていただきたいと考えています。」
【Point】
今の職場を否定するのではなく、「ここで学んだからこそ、次のステップが見えた」というストーリーで語るのがコツです。これなら、師長も「あなたの将来のためなら…」と、応援せざるを得ません。
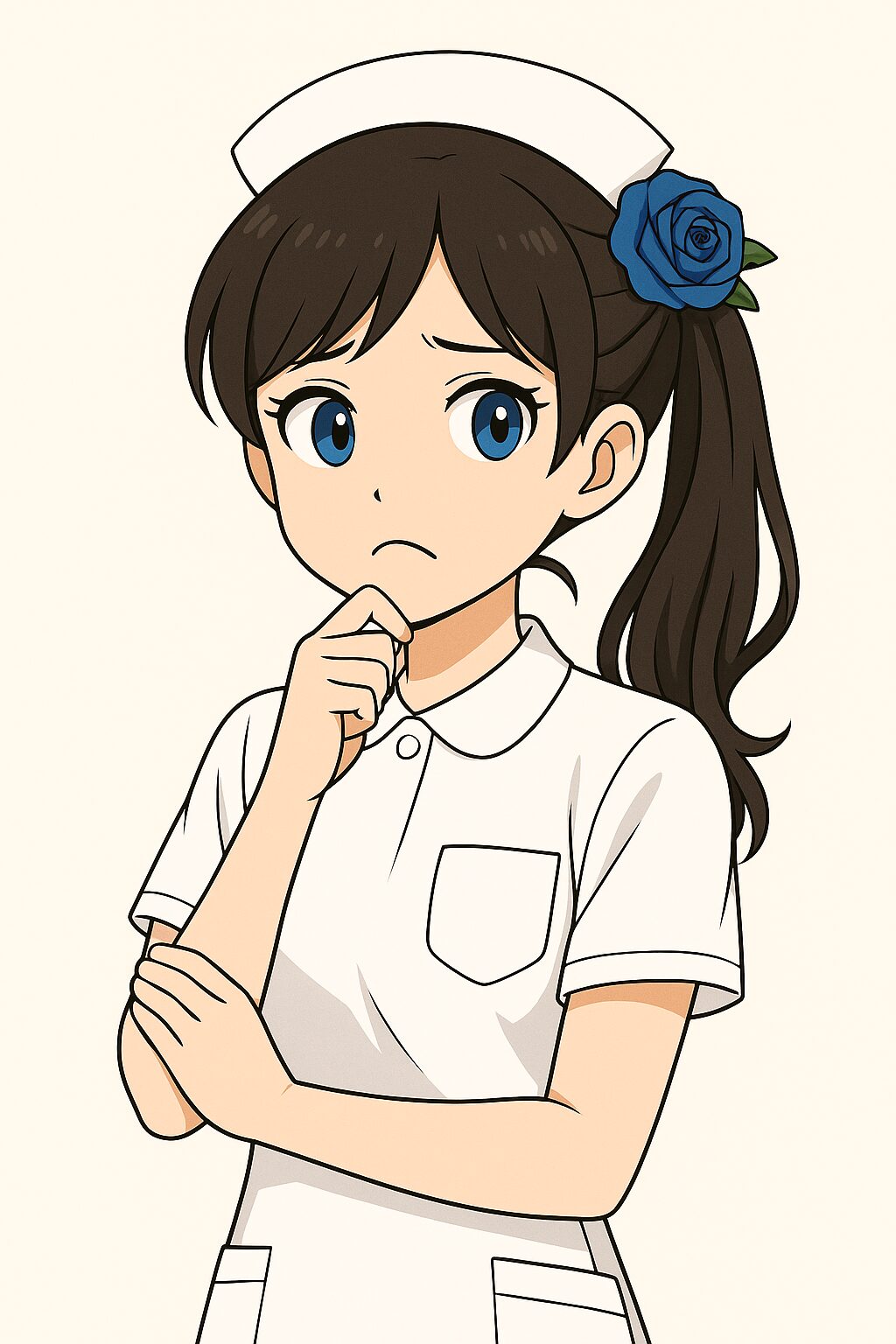
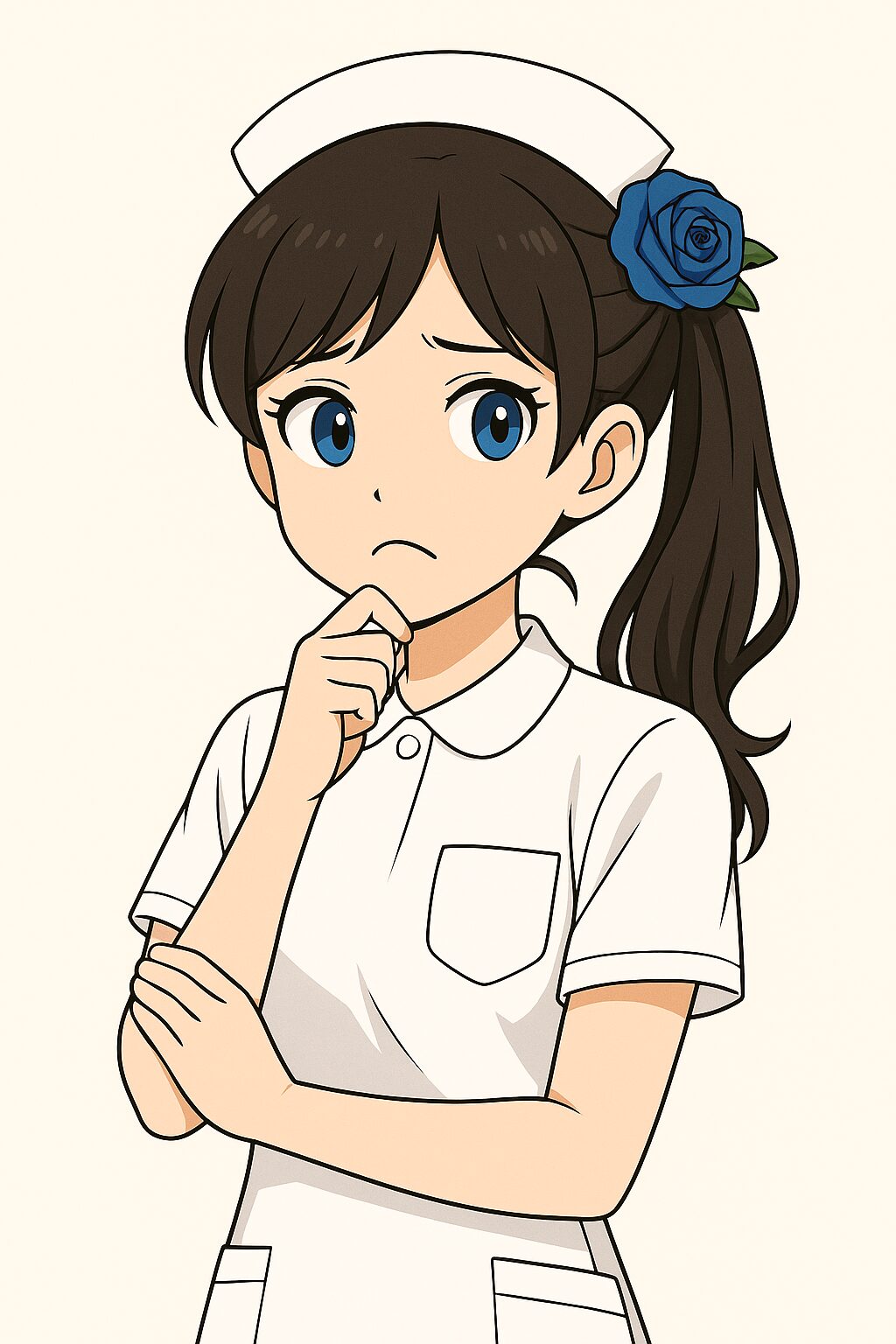
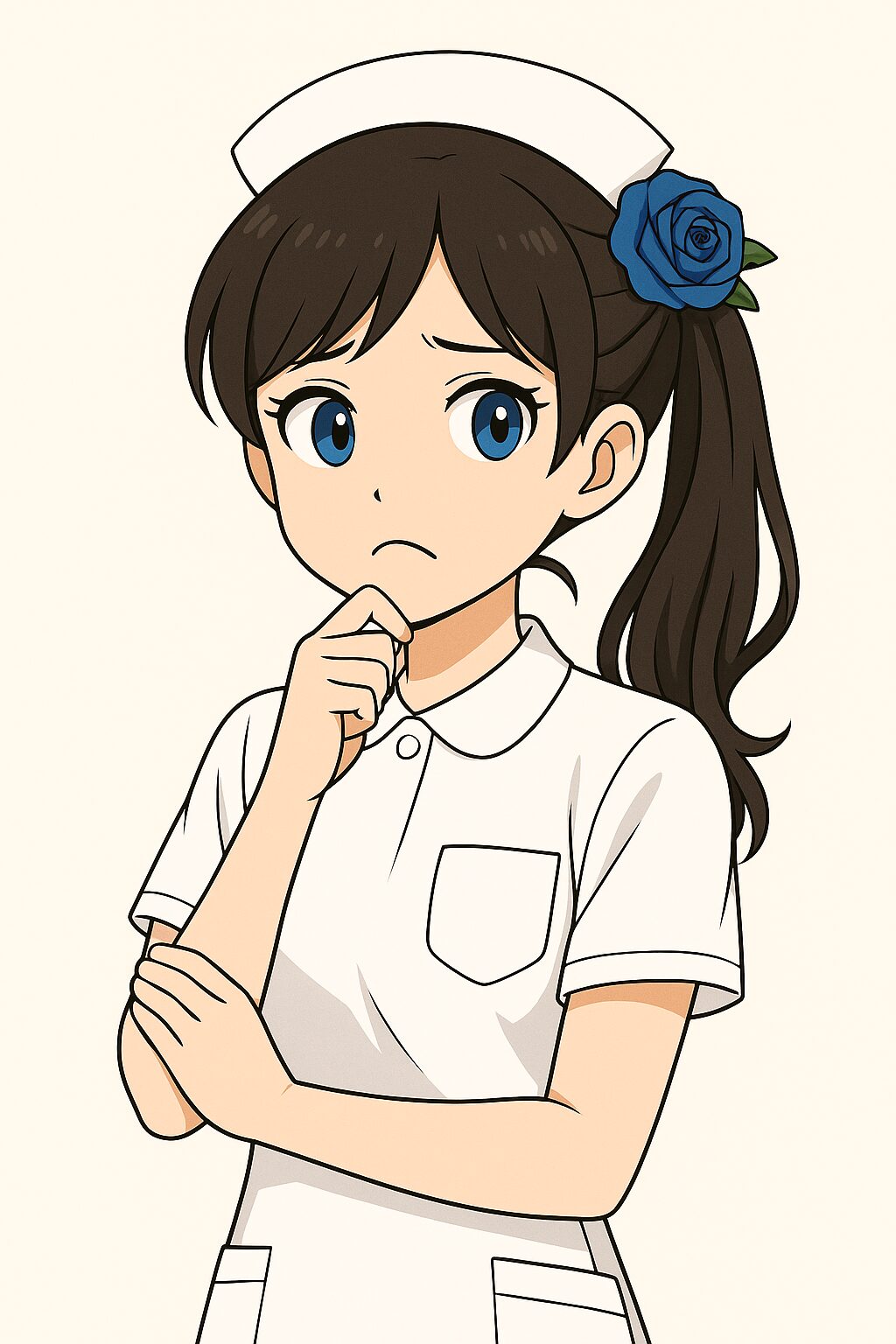
ただ、新人さんや経験の浅いナースだと、「ここで学んだからこそ、次のステップが見えた」という理由は使えないですよね…。
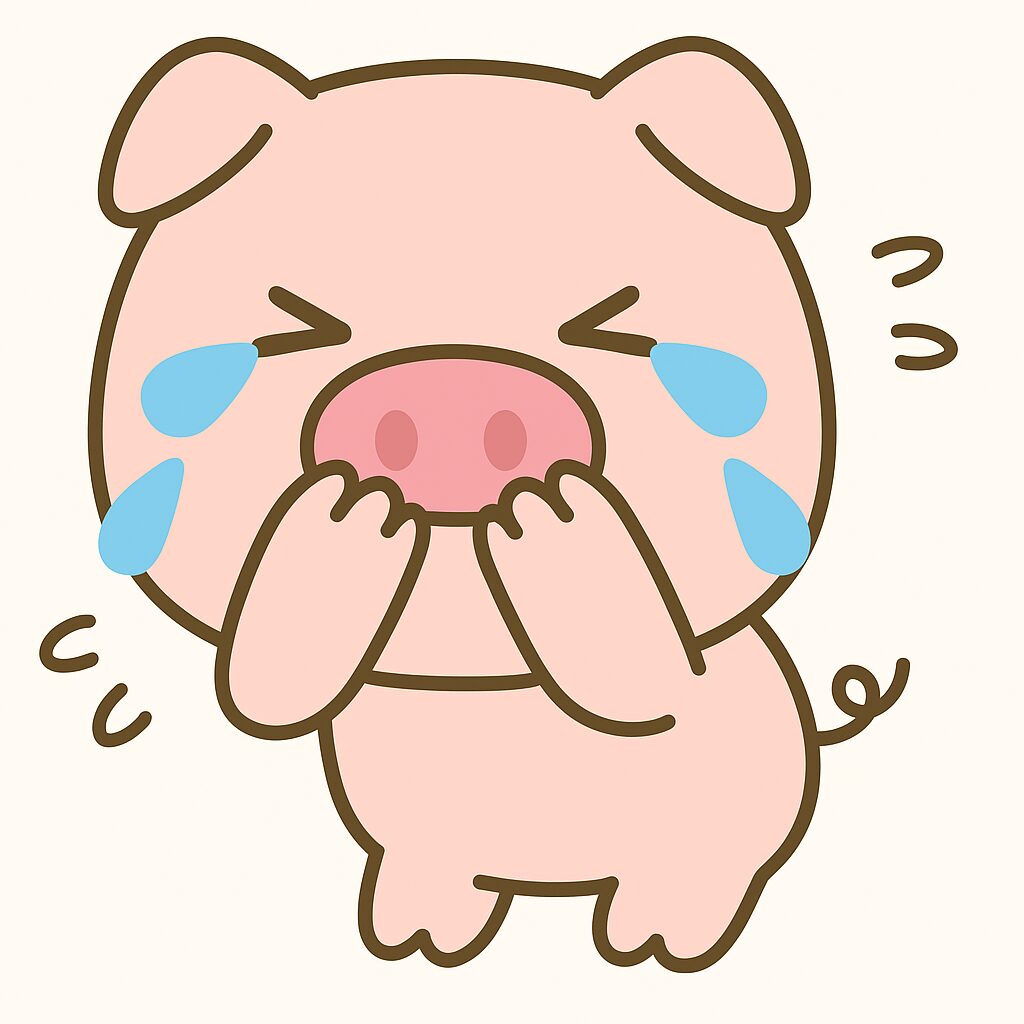
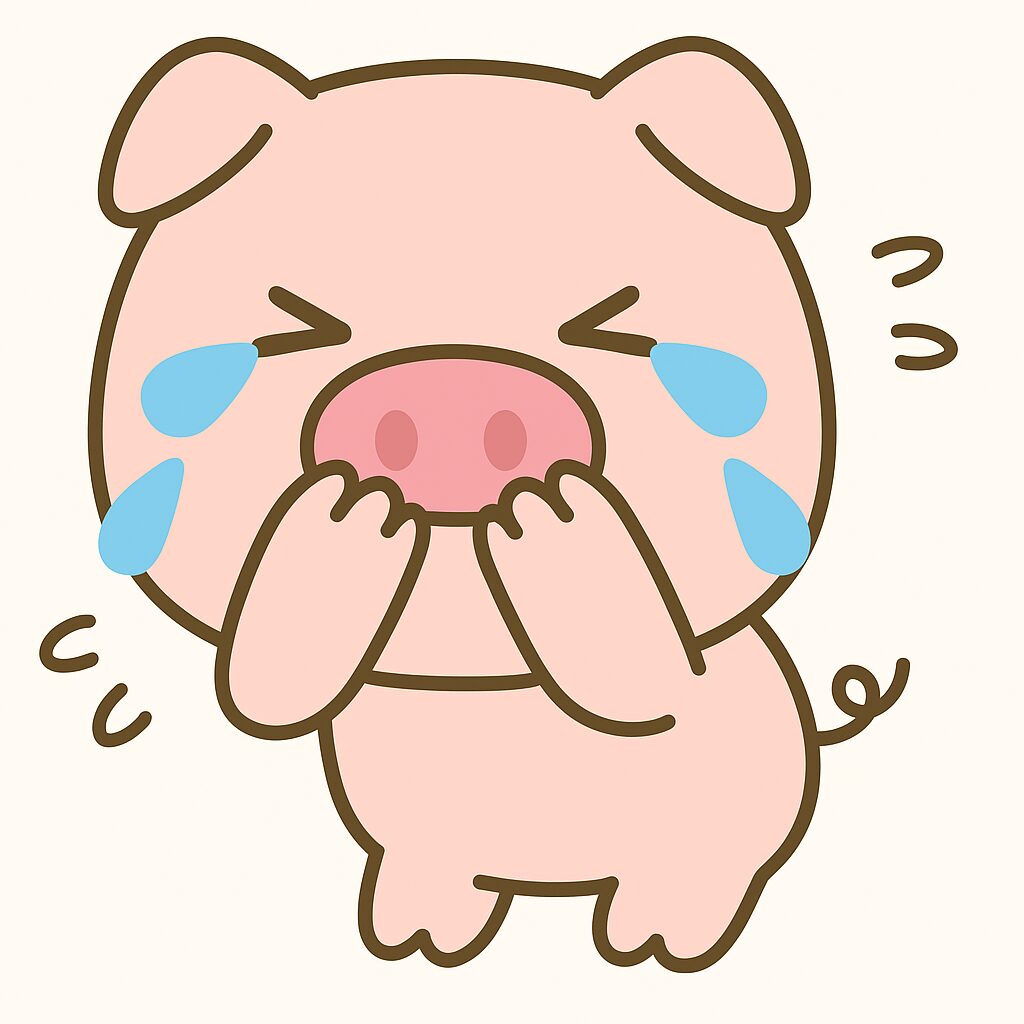
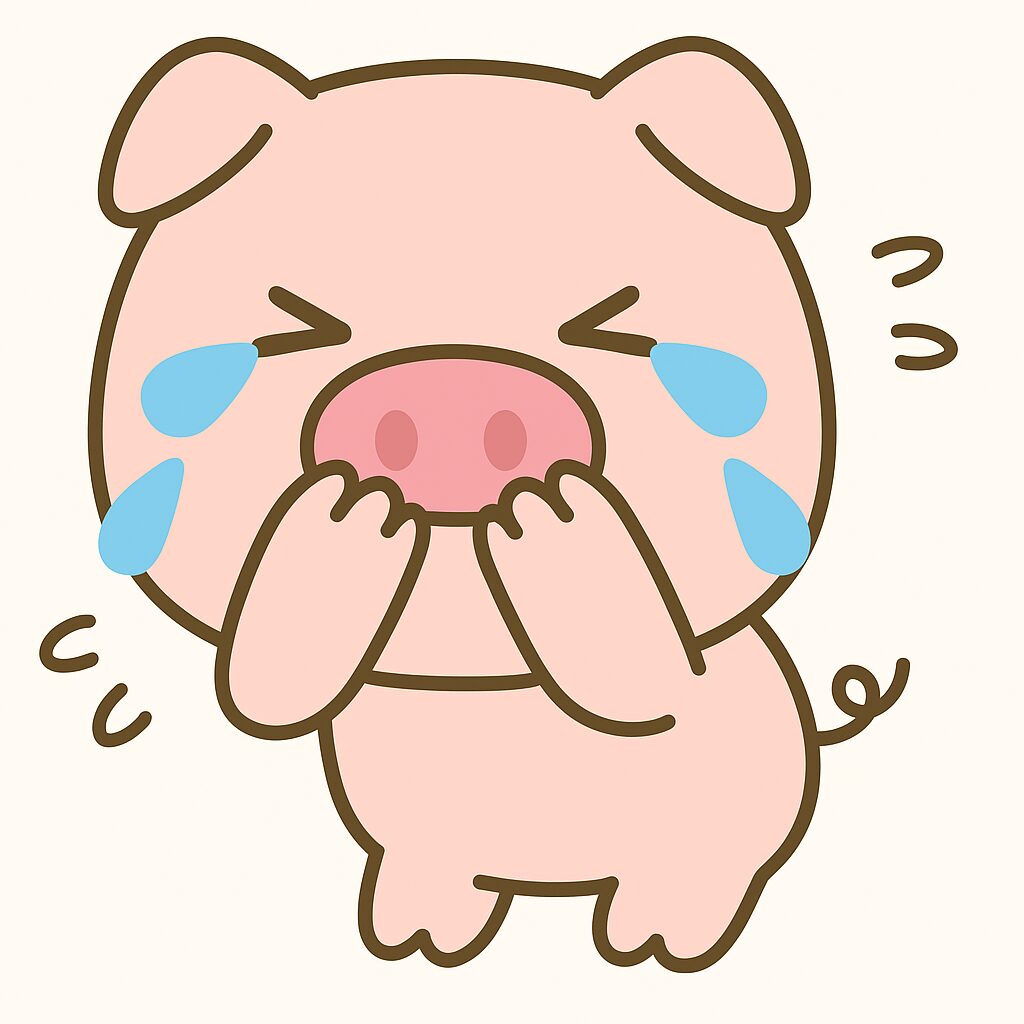
「まだここで学べることがあるでしょ」と、説得されそう
② 相性型:「働き方や環境が、自分に合っていない」
新人さんや経験の浅い方の場合、「スキルアップ」では説得力が弱いと感じることもあります。
そんなときは、“相性の問題”として伝えるのが有効です。
【例文:『相性』を理由にする場合】
「お時間をいただきありがとうございます。みなさんには大変よくしていただき、感謝しています。ただ、実際に働かせていただく中で、どうしても、この急性期のスピード感や、求められる役割に、私の性格とどうしても合っていないと感じる場面が多く、このままでは、かえってみなさんにご迷惑をおかけしてしまうと思い、退職しようと決めました。
【Point】
これは、「私には、この職場は合わなかった」という、誰にも否定できない「事実」を伝えるテクニックです。あなたの能力不足を責めるわけでも、職場を批判するわけでもない。だから、上司は、引き止める理由を探しにくいのです。
② やむを得ない事情型:「健康や家庭の事情」を理由にする
プライベートな事情は、引き止められにくい理由の一つです。ただし、伝え方は慎重に。
【例文:健康上の事情を伝える場合】
「最近、体調を崩し、医師からも『しばらく、休養を優先するように』と診断を受けました。勝手ではありますが、治療に専念するため、退職させていただきたいと考えています」
【Point】
医師の診断書がある場合、それはあなたの心強い“武器”になります。無理せず、自分を守る選択をして大丈夫です。



本音を全部伝える必要はありません。
でも、“嘘をつかず、誰も責めない”というラインなら、納得して
話しやすいです。



伝え方は、「退職後の印象」にも影響します。
少し勇気を出して、「自分の未来のためにがんばろう」と思って、
準備してみてください。
【第三章】防衛編:「引き止め」への完全対処マニュアル
「辞めたい」と伝えた瞬間から始まるものといえば?
そう、「引き止め」です。
特に看護の世界では、理屈よりも“感情”に訴える引き止めトーク*が多いのが特徴。
でも安心してください。よくあるパターンと、それに対する“冷静かつ誠実な返し方”を知っておけば、慌てず対応できます。



この章では、看護師ならではの「リアルな引き止め」とその乗り越え方を、セリフ付きの具体例で解説していきます。
【看護師退職時の「引き止めトーク」と、その解答例】
- 感情論タイプ:「あなたがいなくなったら、患者さんが困るじゃない!」
- 解答例:「私の決断で、スタッフの皆さんや患者さんにご迷惑をおかけすることは、本当に心苦しく思っています。ですが、自分の人生を真剣に考えた上で、決めたことです。本当に申し訳ありません」



ポイントは、相手の感情を受け止めつつも、自分の決意は変わらない
という軸をブラさないことです。
- 同調圧力タイプ:「みんな大変な状況なのに、あなただけ辞めるの?」
- 解答例:「皆さんが大変な状況の中で頑張っていること、はよくわかっているつもりです。だからこそ、残りの期間で、しっかりと引き継ぎをして、迷惑を最小限にできるよう、精一杯努力するつもりです」



ポイントは、「あなただけ辞めるのか?」という論点を、「だからこそ、
最後まで責任を果たす」と、誠実に返すことです。
- 条件提示タイプ:「給料を上げる・待遇改善するから、残ってくれないか?」
もし、上司からこれを言われたら、心の中で、ガッツポーズをしてください(笑)
なぜなら、その瞬間、この交渉のパワーバランスは、完全にあなたに傾いたからです。
この言葉は、「交渉のテーブル」が開かれた合図です。
ここからは、2つの選択肢があります。- 選択肢①:条件改善を検討する
条件提示をされたからといって、その場ですぐに答える必要はありません。
「今すぐ決めてほしい」と言われても、いったん冷静になるのが得策です。
仮に年収が数十万円アップするなど魅力的な話だったとしても
──その条件が、本当に今感じている不満(人間関係・働き方・将来の不安)を上回るかどうか。一度持ち帰って、じっくり考えてみることをおすすめします。
- 選択肢①:条件改善を検討する



ここで「それなら残ります」と即答してしまうと、あとから「やっぱり辞めたい…」と感じても、もう引き返せません。
・だからこそ、このパターンになったら、選ぶべきは「後出しジャンケン」です。
提示された条件が、あなたの今感じている不満(人間関係・働き方・将来の不安)を上回るほど魅力的だった場合。
「…正直、これならもう少し頑張れるかも」
そんなふうに、あなたの中で気持ちが変わるなら──
残るという選択肢も、まったく問題ありません。
それは、あなたが勇気を出して“退職する”という行動を起こしたからこそ得られた成果なんです!
逆に──
「やっぱり自分にとってベストなのは、退職だ」と判断したなら──
以下の選択肢になります。
- 選択肢②:提案に感謝を示しつつ、やっぱり退職する
- 解答例:「大変ありがたいお話を頂き、本当に感謝しております。ですが、今回の決断は、条件面だけが理由ではありません。自分の今後のキャリアを考えた上での、真剣な決断です。本当に、申し訳ありません」
- 解答例:「大変ありがたいお話を頂き、本当に感謝しております。ですが、今回の決断は、条件面だけが理由ではありません。自分の今後のキャリアを考えた上での、真剣な決断です。本当に、申し訳ありません」



ポイントは、「病院や待遇の問題ではない」という姿勢で、説得の材料を相手に与えないことです。
【第四章】どうしても難しい場合の“安心できる選択肢”
ここまでお伝えした工夫をしても、「やっぱり一人で師長に伝える勇気が出ない」「引き止めに耐えきれない」
と感じる方もいるかもしれません。
そんなときには、退職代行という選択肢もあります。
退職代行は「逃げ」ではなく、あなたを守るためのセーフティーネットです。
- 上司への直接の伝達を代わりにしてくれる
- 退職届の提出や日程調整のサポートをしてくれる
- 感情的な衝突を避け、冷静に退職を進められる
もちろん、まずは自分で誠実に伝える努力が大切です。
でも、「どうしても無理」「精神的に限界」というときに備えて、こうした手段があると知っているだけで、心の余裕が変わります。



実際に退職代行を使って辞めることができた体験談は、こちらの記事で
詳しく紹介しています。
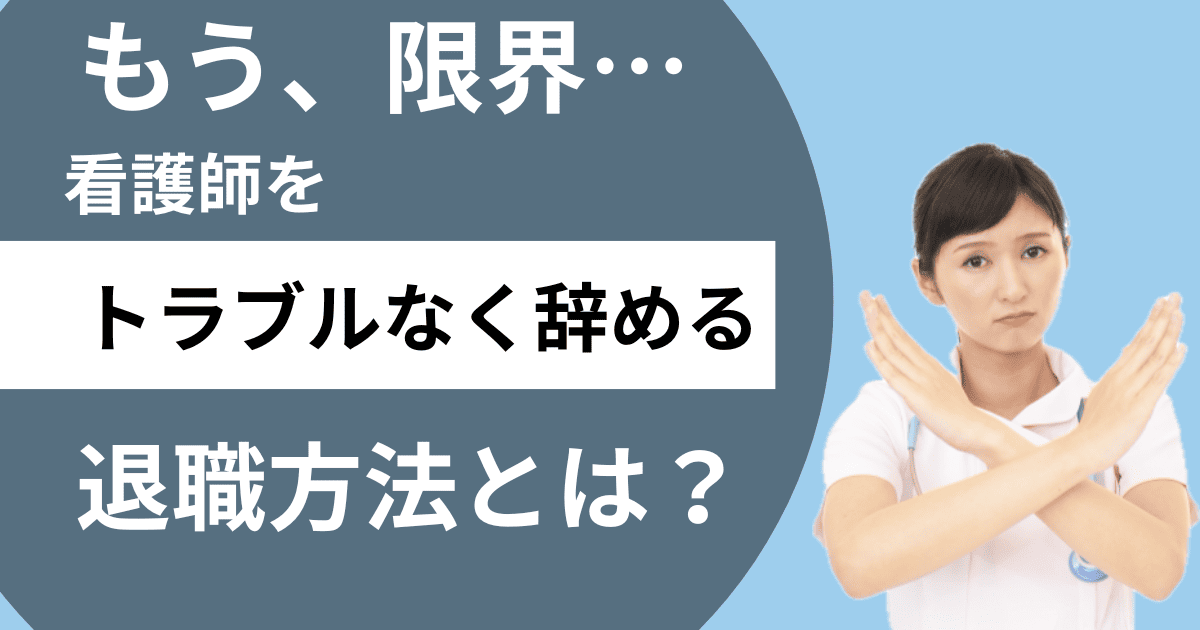
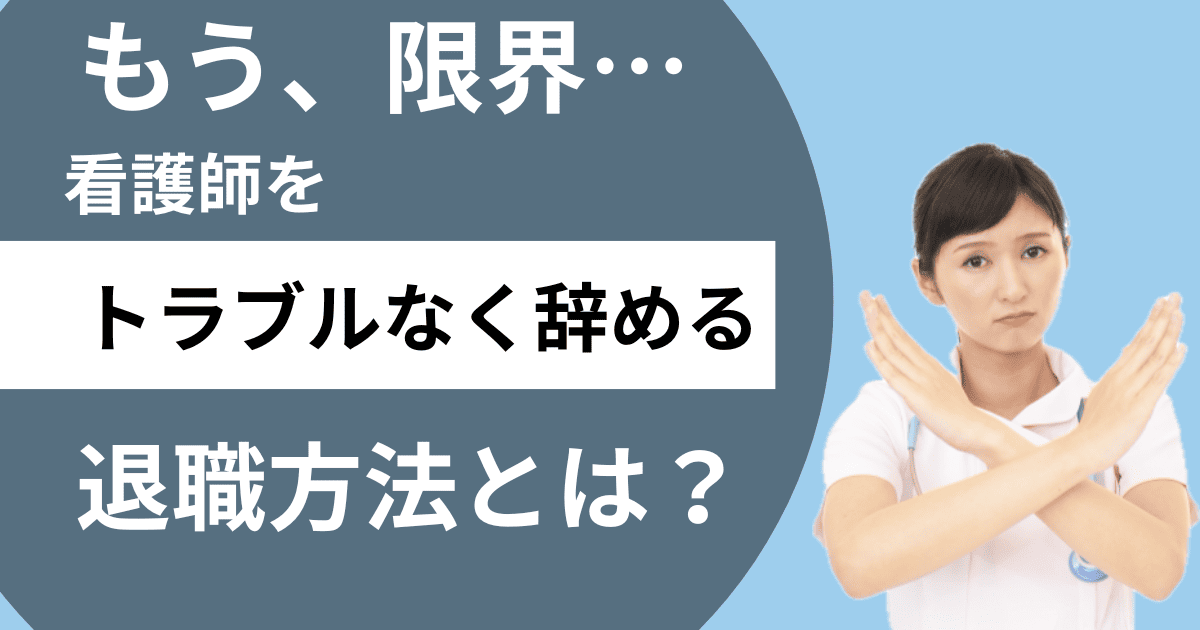
【第五章】完結編:最後の瞬間まで、あなたはプロフェッショナルであれ
退職日が近づいてくると、「ようやく終わる…」と気が抜けてしまうかもしれません。
でも、実はこの最後の数日こそ、あなたの印象がグッと良く残るか、台無しになるかの分かれ道なんです。
「終わり良ければ、すべて良し」。
そのために、ムリなくできる範囲で、ちょっとだけ意識してほしいことがあります。
- 責任ある引き継ぎ:「もう辞めるんだから自分には関係ない」。そう思いたくなる気持ちもわかります。あなたが、いなくなった後も現場が回るようにしておけると親切です。
- 具体例を上げると:①業務内容のマニュアル化
②注意点やルールの「引き継ぎ」を紙で残しておく
③新人さんや次の担当者が困らないようにしておく - 挨拶回り:最終出勤日には、お世話になった方々へ、挨拶をしましょう。
- お菓子は「個包装」で「人数より少し多め」に:これが、地味ですが、最も感謝が伝わる心遣いです。



これらのすべてを完璧にやらなくても、その姿勢を見せる
だけで、十分「プロフェッショナル」です!
【まとめ】最高の退職は、最高の転職への、第一歩です
ここまで読み進めてくださり、本当にありがとうございました。
退職というと、どうしても「逃げ」や「ネガティブな選択」と見られがちですが、それは違います。
これは、あなたが“もっと自分らしく働ける場所”に向かって、一歩踏み出すための準備です。
この記事でお伝えしたことをひとつひとつ実践すれば、きっとあなたの退職は「ただ辞める」だけのものではなく、“未来をつくる決断”へと変わっていくはずです。
「うまくいったよ!」
「これは自分には合わなかったかも…」
など、あなたの体験を、ぜひコメントやXのDMで教えてください。
同じように悩んでいる誰かの、ヒントになるかもしれません。
「やっぱり、一人で退職を伝えるのは不安…」そんなあなたへ。
ここまで読んで、「やっぱり、一人で師長さんに退職を伝える勇気が出ない…」と思った方も、どうか無理をしないでください。
看護師向けの転職エージェントの中には、こうした「円満な退職の進め方」についても、具体的にアドバイスしてくれるところがあります。
病院に代わって直接交渉をしてくれるわけではありませんが、
あなたの不安を受け止め、
「どう伝えるか」「どこに注意すべきか」といったポイントを一緒に考えてくれます。



「あなたの決断は、きっと未来のあなたを助けてくれる」──
そう、心から信じています!



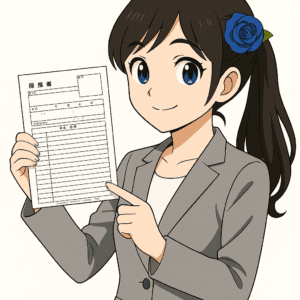





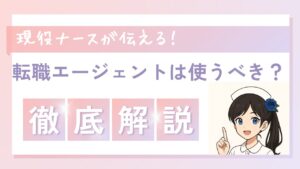
コメント